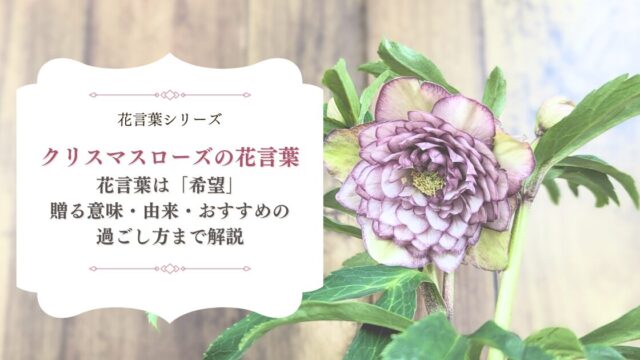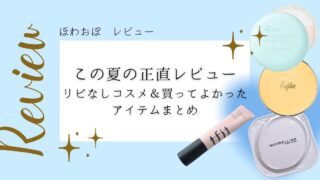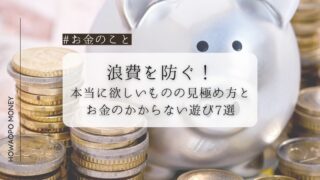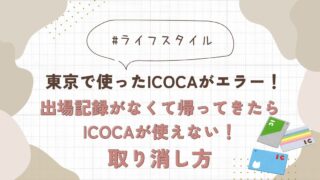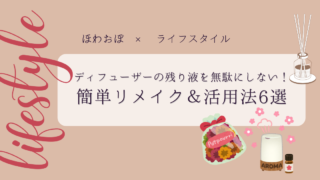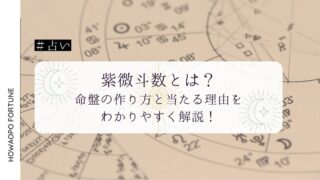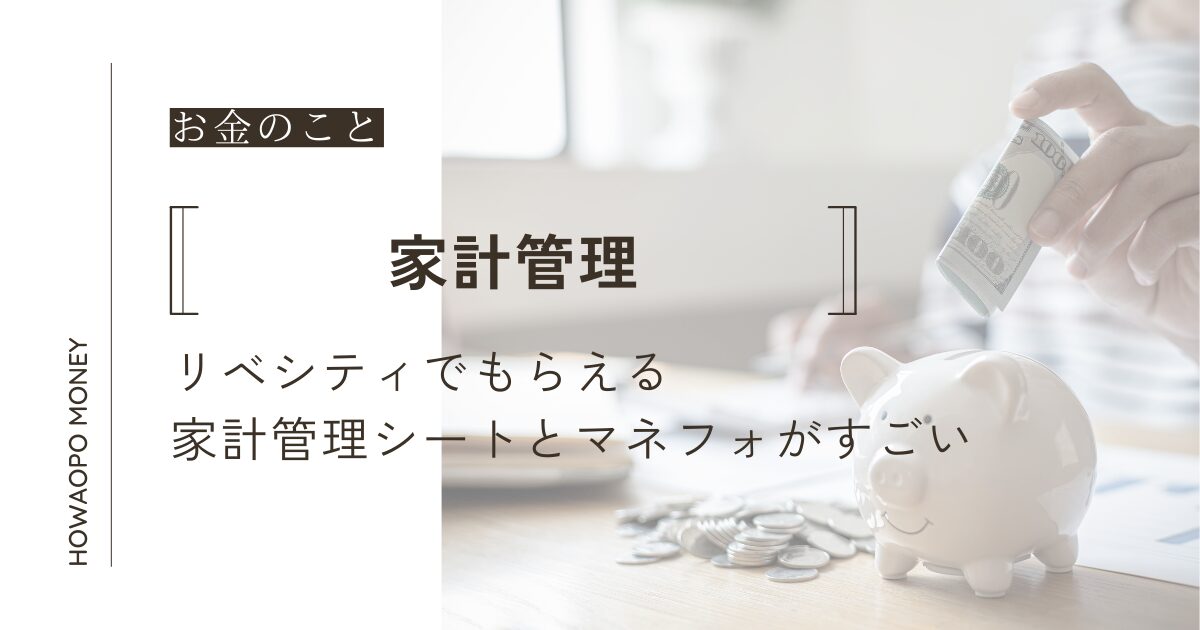花言葉:鬼灯(ほおずき)の花言葉・美容成分・育て方ガイド|観賞用と食用の違いも解説

※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。収益はブログ運営費に充てています。
こんにちは!ほわおぽです🐼♡
夏の風物詩としても親しまれる「鬼灯(ほおずき)」。
赤く透き通るような果実は、まるで提灯のようで、古くから日本人に愛されてきました。
今回は、鬼灯の花言葉や名前の由来、美容に嬉しい成分、そして育て方までまとめてご紹介します。✨
鬼灯の花言葉💌

鬼灯には、いくつかの花言葉があります。
- 偽り
- ごまかし
- 自然美
- 心の平安
透き通る赤い果実が美しい一方で、中身は空洞になっていることから「偽り」「ごまかし」という花言葉がつけられたといわれています。
また、その幻想的な姿から「自然美」「心の平安」といったポジティブな意味も込められています🌿
名前の由来📖
「ほおずき」という名前の由来には諸説あります。
- 果実を口に含んで鳴らす遊びから「頬(ほお)好き」
- 赤く色づく果実が頬の色に似ていることから😊
- 漢字の「鬼灯」は、お盆に鬼の提灯として先祖の霊を導く灯りに見立てられたことから🏮
古くから夏の風物詩やお盆の供え物として大切にされてきた植物です。
お盆での飾り方🎐
お盆には鬼灯を「精霊を導く灯り」として飾ります。
特に赤く色づいた実は、提灯の代わりとして仏壇や盆棚に供えられます。
枝ごと花瓶に生けたり、鉢植えのまま飾ることもあり、夏らしい雰囲気とともに先祖を迎える大切な意味が込められています。
美容成分たっぷり!鬼灯の力🍒

実は、鬼灯には嬉しい栄養素も含まれています。
- ビタミンC:美肌や免疫力アップに🍋
- カロテノイド:抗酸化作用でアンチエイジング効果✨
- ビタミンA:皮膚や粘膜を健やかに保ち、視力維持にも役立つ👀
- ポリフェノール:活性酸素を抑え、健康維持に役立つ💪
昔から民間薬としても利用され、咳止めや解熱に使われることもありました。
また、果実や根を煎じて利尿や喉の炎症の改善に用いられたり、産後の回復を助ける薬草としても伝えられています。美容にも健康にも一目置かれる植物です。
※医薬品としての効能を保証するものではありません🌿💊
観賞用と食用の違い🍽️
鬼灯には観賞用と食用の2種類があります。
- 観賞用:一般的にお盆や観賞に使われる品種で、実は苦味が強く食用には適しません。
- 食用ほおずき(フィサリスなど):黄色やオレンジ色の実をつけ、甘酸っぱくフルーツのような味わい。ジャムやお菓子、サラダに利用されます。🥭
見た目は似ていますが、用途が大きく異なるため、購入や栽培の際は区別することが大切です。
鬼灯の育て方🌱
鬼灯は丈夫で育てやすい植物です。初心者の方にもおすすめ!
基本情報
- 科名:ナス科
- 開花期:6月〜7月
- 実の鑑賞期:7月〜9月
育て方のポイント
- 日当たりと風通し:日当たりのよい場所で育てましょう。半日陰でも可☀️
- 土:水はけの良い土を好みます。市販の培養土でOK🪴
- 水やり:乾いたらたっぷり与える。過湿に注意💧
- 冬越し:多年草なので地植えならそのまま冬越し可能。鉢植えは寒さを避けて管理を❄️
- 増やし方:地下茎でよく増えます。株分けで簡単に増やせるのも魅力🌸
まとめ📝
鬼灯は、幻想的な見た目だけでなく、花言葉や由来に深い意味を持ち、美容・健康にも嬉しい成分を秘めた植物です。
育てやすさも魅力で、庭や鉢植えに取り入れれば夏の彩りをぐっと引き立ててくれます。
ぜひ、鬼灯の奥深い魅力を生活に取り入れてみてくださいね!
最後まで読んでくださりありがとうございました✨